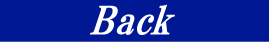過去の定例会情報はこちら
主な質問・質疑
●
定例会を終わって ●主な質問・質疑 ●
会期日程 ●
本会議一般質問 ●意見書・決議 ●議員提案条例
平成15年11月定例会本会議での一般質問の主な内容は次のとおりです。
各常任委員会の委員長報告要旨については、こちらをクリックしてください。
| |
国と地方の税財政改革である「三位一体の改革」について、本県にどの程度の影響があると考えているのかと質した。
県側の答弁
三位一体の改革は、地方分権の推進と持続可能な財政構造への転換に向けて、避けて通れない課題であると考えている。
しかし、改革に当たっては、まず、国・県・市町村の役割分担を明確にした上で、それぞれの役割に応じた財源配分のあり方を検討していくべきである。特に、教育や福祉、警察、消防などの分野については、全国で一定の行政水準を確保できるよう国の責任で財源を措置すべきものであり、慎重な検討が必要であると考えている。
また、国庫補助負担金の削減と税源移譲により、自治体間の財政力の格差が拡大すると考えられ、これを地方交付税等によってどのように調整を行うかが、大きな課題となる。
現在、国においては、平成16年度に国庫補助負担金1兆円の廃止、縮減に向けて具体的な内容の検討が行われているが、国・県・市町村の役割分担や地方への財源措置のあり方を明確にしないままに、削減の規模のみが優先されているという印象であり、地方の実態を十分に踏まえた議論が行われるよう、引き続き検討内容を注視して、本県に与える影響を検証しながら対応してまいりたい。 |
| |
今回の「大村湾環境保全・活性化行動計画案」の基本的な方向性並びに計画推進の特色はどういうところにあるのかと質した。
県側の答弁
大村湾の環境保全・活性化行動計画の策定に当たって、希少野生生物である「スナメリ」を大村湾の良好な自然環境や多様な生態系のシンボルと位置づけ、「スナメリと共にくらせる湖(うみ)づくり」を計画の副題として掲げている。
その上で、スナメリとの共生を目指す基本的な方向として、
○流域全体の総合的な視点での「大村湾の海、山、川を一体としてとらえた総合的な環境保全の推進」、
○身近な自然を見つめ、楽しむ視点での「自然とふれあえる大村湾の再発見」、
○自然資源や既存施設等を活用する視点での「大村湾の特性を活かした水産や観光などの産業の振興」、
○これらを推進するための最重要課題である「大村湾の自然と環境をまもり育む住民参加の促進」
の4つの柱を計画案に明示している。
計画の推進に当たり、地域の住民・事業者・行政の一体的な取り組みが不可欠であると認識しており、県、流域市町、事業者、住民、関係団体等からなる「大村湾域全体の推進組織」をつくり、関係施策・事業の相互調整や進行管理を行うとともに、住民の参加促進のための広報キャンペーン活動の展開を図ることとしている。 |
| |
国営諫早湾干拓事業は、平成15年度までに94.6%の進捗状況になり、平成18年度の完成を目標に取り組まれているが、干拓農地の機能や農地の価格等、完成後の農地の取り扱いについて質した。
県側の答弁
平成12年度に総合農林試験場が中央干拓地内で試験栽培を開始し、緑肥作物の栽培とすき込みによる土づくり対策等を行うとともに、たまねぎ等の野菜類やきく等の花き類の試験栽培を行い、その結果は、背後地や県内産地と比較しても遜色のない成績を上げており、今後、干拓地の土づくりを進めることにより、生産性の高い優良な畑地帯になるものと考えている。
諫早湾干拓農地の配分価格は、干拓農地に関する受益者負担額、配分農地面積から試算すると、10アール当たり平均70万円台となるが、最終的な配分価格は、今後、農林水産省との調整を経て決定される。
また、干拓地の農地利用については、「低コストな農業生産」、「環境に配慮した農業」、「生産から加工、流通、都市との交流」といった観点で、先進的な農業に取り組む農業者の参画しやすい環境づくりが重要であり、その一つの方法として、農地リース制度の導入についても検討を進めている段階である。
今後、これらの農地の土地利用や配分方法、管理体制などについては、農業者等を対象として実施する意向調査の結果を参考にしながら、国と合同で設置した農地利活用プロジェクトチームの中で十分な検討を行ってまいりたい。 |
| |
合併特例法の期限切れとなる平成17年4月以降の合併については、県はどのように考えているのかと質した。
県側の答弁
合併特例法の期限後の市町村合併の推進については、先般、地方制度調査会の最終答申に示され、合併推進の手法として、県が新たに構想をつくること、知事の勧告やあっせんでの地域自治組織制度の創設及び、新法でも合併に至らなかった市町村に関する特例的団体制度の導入などが盛り込まれている。
しかしながら、その具体的な内容については不透明な部分が多く、県としては、法制化に向けた国の動きを見ながら、今後の対応を検討してまいりたい。
自主財源に乏しく国への依存度が高い小規模自治体は、今後、地方交付税や補助金の抜本的な見直しが行われると、行財政運営上、相当厳しい状況に置かれるものと考えられることから、平成17年4月以降、小規模自治体が合併せざるを得ない状況に陥ることも想定される。
その時には、財政的支援がないということをお考えいただきたい。
県としては、将来のまちづくりのため、合併特例債や交付税、補助金などの優遇措置がある現行特例法の期限内に小規模自治体が合併を実現されるよう、引き続き助言、調整に努めてまいりたい。 |
| |
九州新幹線長崎ルートは、現在どのような状況にあるのかと質した。
県側の答弁
整備新幹線の新たな着工区間については、九州新幹線新八代-西鹿児島間の完成後に見直すこととされており、現在、与党間で整備新幹線建設促進プロジェクトチームが設置され、未着工区間の取り扱いに関する与党案の取りまとめのための協議が進められている。
12月5日には、副議長と副知事が福岡、佐賀、長崎3県の自治体、経済界の方と上京し、与党整備新幹線建設促進プロジェクトチームの久間座長などに対し、武雄温泉-長崎間の認可とともに、長崎駅の整備に加え、武雄温泉-新大村-諌早間の建設費を認める内容とするなど、ルート建設の方向性を明確にしてほしい旨を強く要望した。
さらに、10日及び16日には、知事も県議会議長等と上京し、福岡、佐賀、長崎の3県による要望活動を政府・与党幹部などに行うとともに、本県選出国会議員に対する長崎新幹線早期着工の強力な支援をお願いした。
一般質問後の状況
政府・与党は、平成15年12月22日に整備新幹線の整備について、与党整備新幹線建設促進プロジェクトチームの整備に必要な財源等の結論を得た上で、政府与党からなる検討委員会で平成17年度予算編成課程での安定的な財源の確保、具体的な新規着工区間の着工のあり方等について検討を行い、基本条件の確認をした上で認可するとの合意に達しています。 |
| |
県の中期財政見込みによると、平成20年度末には144億円の歳入不足が生じることが予測されている一方、県税の滞納が平成14年度約28億円に達していることから、税務行政の公平を期する上で、徴収率を高めるために、具体的にどのような行政努力をしてきたのかと質した。
県側の答弁
住民税に関しては県税、市町村税を一括して市町村が徴収するが、共同催告、共同徴収を22市町で実施するとともに、休日、夜間の窓口開設、あるいは訪問徴収を強化するなど、職員一丸となって対応している。
大口や悪質な滞納者については、粘り強く説得を重ね、応じない場合には、直ちに差し押さえ処分を講じるという強い姿勢で臨んでいる。
この結果、差し押さえ件数は、預金や給与など1,178件となっており、前年より63件増加した。
職員の資質向上については、徴収技術の習得のため国への研修派遣などを行っている。
また、住民税の収入確保、あるいは市町村職員の徴税技術の向上を目的として、県職員が市町村の職員と併任という形で、徴収事務に従事する制度をつくり、今年度からスタートさせた。
なお、市町村で対応できなかった場合に、依頼があれば県が徴収に出向くという地方税法第48条に基づく要請があった市町村については、順次、対応してまいりたい。 |
| |
○「あらゆる地域の国民が身近で充実した司法サービスを受けられる司法改革を求める意見書の採択に関する請願書」 |
| |
○あらゆる地域の国民が身近で充実した司法サービスを受けられる司法改革を求める意見書
○自衛隊のイラク派遣に関する意見書
○景気・雇用対策についての意見書
|
| |
| 【知事提出の議案】 |
| ・予算 |
7件 |
(可決) |
| ・条例 |
14件 |
(可決) |
| ・事件(契約等) |
13件 |
(可決) |
| ・人事 |
2件 |
(同意) |
| ・報告 |
1件 |
(承認) |
| ・決算 |
1件 |
(認定) |
|
|
|
| 【議員等提出の議案等】 |
| ・条例 |
1件 |
(可決) |
| ・意見書 |
3件 |
(可決) |
|
|
|
| 【請願】 |
1件 |
(採択) |
|
1件 |
(不採択) |
|
|