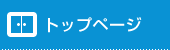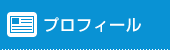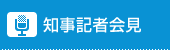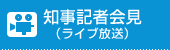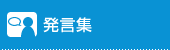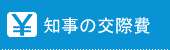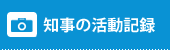長崎県ホームページ
パンくずリスト(現在位置の表示)
知事のページ - 長崎県知事 大石賢吾
令和7年2月21日 令和7年2月定例県議会における知事説明
本日、ここに、令和7年2月定例県議会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 説明に入ります前に、去る12月29日、韓国・全羅(ぜんら)南道(なんどう)の務安(ムアン)国際空港で発生した航空機の事故により、179名の方々がお亡くなりになられました。 本県と深い友好交流の絆で結ばれている韓国において、多数の尊い命が失われたことは、本県にとっても悲しみに堪えません。 県民を代表して、お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆様に、心から哀悼の意を表しますとともに、負傷された方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。 それでは、開会に当たり、県政運営についての所信を申し述べますとともに、令和7年度当初予算案について、その概要をご説明申し上げます。
長引く物価高騰への対応
本県の経済は、生産活動の持ち直しや所得環境の改善などから、「緩やかに回復している」とされ、最新の有効求人倍率は、1.19倍と雇用情勢も堅調に推移している状況にあります。 一方で、円安等によりエネルギー・食料品等の価格が高止まりしており、各産業分野における人手不足と相まって、県民生活はもとより、地域を支える中小・小規模事業者や第一次産業従事者など、様々な事業者の経済活動に影響を及ぼしております。 こうした中、国においては、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が策定され、昨年12月に物価高騰への対策を含む関連補正予算が成立いたしました。 これを受け、本県でも、先の11月定例会において、国の交付金等を活用のうえ、医療・福祉施設や学校等へのエネルギー価格・食材料費等の支援のほか、農林水産業におけるセーフティネットへの支援などの物価高騰対策等にかかる補正予算を編成し、速やかな執行に努めております。 県民の皆様の生活を豊かにするためには、その基盤となる経済をしっかりと回していくことが何よりも重要であります。 そのため、物価高騰を踏まえた生活者支援や事業者の生産性向上等についても、さらなる対策を講じていく必要があると考えており、本定例会において、市町と連携したプレミアム商品券の発行や生産性向上のための設備等の導入支援など、追加の経済対策を盛り込んだ関連予算を提案しております。 引き続き、社会経済情勢を注視しながら、県民生活を下支えし、県内経済活動の活性化に資する施策の推進に力を尽くしてまいります。
県総合計画の総仕上げと新しい長崎県づくりのビジョンの推進
令和7年度は、「長崎県総合計画 チェンジ&チャレンジ2025」の最終年度にあたり、私にとりましても、知事として任期の最終年度となります。 県政の基本方針であります総合計画については、知事就任後、行政の継続性を重視し、当計画に掲げる、「人が活躍し支えあう」、「産業が育ち活力を生む」、「地域がつながり安心が広がる」の3つの柱に沿って、県民や市町、民間団体、大学等の皆様と、相互に連携・協働しながら、各種施策を積極的に推進してまいりました。 具体的には、戦略的な企業誘致等による魅力的な働く場の確保や、農林水産業の生産性向上、移住対策の充実等について取り組み、その結果、企業誘致等による雇用創出や、農業産出額及び県外からの移住者数の増加などの成果につながっております。 併せて、西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業など「まち」の佇まいが大きく変わるプロジェクトが進展するとともに、大手企業の製造拠点の立地や、半導体・航空機・海洋エネルギーの関連産業といった成長分野における新たな動きなど、産業構造にも変化が生じており、まさに本県は大きな変革の時期を迎えております。 こうした機会をチャンスと捉え、今後の県勢のさらなる発展につなげるためにも、令和7年度は、本計画の総仕上げに向け、成果の出ている施策はこれまで以上に伸ばし、課題が残っている施策は、対策の強化を図ってまいります。 また、将来への不安や憂いを払拭し、本県への誇りや未来への期待感を持ち、新しい長崎県を築いていきたいとの思いから「新しい長崎県づくりのビジョン」を策定し、重点的に取り組む分野として、「こども」「交流」「イノベーション」「食」の4つの柱を掲げ、様々な関係者とともに、各種取組を進めております。 こうした中、「こども」分野においては、子どもが主役の居場所づくりに向けた民間との連携関係の構築を図るとともに、保育人材の確保対策として、園内研修に取り組む施設に対し、保育士等の処遇改善を支援する県独自の制度の創設を実現することができました。 さらに、「イノベーション」分野においては、ドローンを活用した地域課題の解決に向け、人材育成や基盤づくりに努めるとともに、国に対し、規制改革を訴えてまいりました。 その結果、昨年、全国で初めてとなる「新技術実装連携“絆”特区」の指定を受けることができ、現在、ドローンサービス事業者の有人地帯での目視外飛行等による医薬品配送や、インフラ点検等の実証調査など、先進的な取組が進展しているところであります。 令和7年度においては、引き続き、様々な立場の方々に共感いただきながら、部局横断・融合した施策のさらなる推進を図り、ビジョンの各分野で相乗効果を生み出し、県民の皆様が、「こうなったらいいな」と思う世界である「未来大国」の実現に向け、力を注いでまいりたいと考えております。
節目の年、飛躍の年
令和7年は、被爆80年をはじめ、日韓国交正常化60年、長崎空港開港50周年、中華人民共和国駐長崎総領事館開設40周年など様々な節目の年にあたります。 また、全国規模の文化の祭典「ながさきピース文化祭2025(にせんにじゅうご)」や、国際サイクルロードレース「ツール・ド・九州2025」などの大型イベントが県内各地で開催され、大阪では、全世界から集客が見込まれる「大阪・関西万博」も予定されております。 さらに、長年、被爆体験の継承と核兵器の廃絶に取り組んでこられた日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞により、「核兵器のない世界の実現」への機運がこれまで以上に高まっていると認識しております。 こうした機会や機運の高まりをしっかりと捉え、本県の持つ多彩な魅力を磨き上げ、発信することで、国内外の多方面の方々から「選ばれる長崎県」を目指してまいります。 加えて、長年培ってきた各国との友好交流や平和発信等をさらに促進させるなど、本年が、県勢のさらなる発展につながる飛躍の年となるよう、新しい発想や視点も積極的に取り込みながら、私自らが先頭に立ち、県民の皆様や職員と一丸となって、各種施策を力強く展開してまいりたいと考えております。 どうか県民や県議会の皆様には、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 このような基本的姿勢に基づく、新年度の主な施策について、5つの重点テーマの柱に沿って、具体的にご説明いたします。
令和7年度 長崎県の主要施策〜選ばれる「新しい長崎県」の実現に向けて〜
1.子どもが夢や希望を持って健やかに成長できる社会の実現
(「こども場所」の充実と「こども時間」の確保)子どもたちの未来は長崎県の未来そのものであり、本県の明るい未来を築いていくため、子どもたちへの投資を未来への投資と捉えたうえで、将来を担う子どもたちが健やかに成長し、多様な活躍につながる社会の実現を目指してまいりたいと考えております。 そのため、安全・安心で多様な居場所や、冒険などチャレンジできる体験を提供する「こども場所」の充実に向け、官民ネットワークの構築や中間支援組織の設置等と併せ、新たに「長崎県こども未来応援基金」を創設し、居場所の立ち上げやモデルとなる多様な体験の場づくりを支援してまいります。 このほか、こども食堂に対して支援を行う市町への補助制度の創設や、子ども施策について子どもの意見を聞く機会を設けるなど、官民一体となり、子どもの自己肯定感を高め、子どもが主役の長崎県の実現を目指してまいります。 また、近年増加傾向にある不登校児童生徒のため、小中学校における校内教育支援センターの設置促進や、オンラインによる支援体制強化などにより、ニーズに応じた多様な学びの場の確保・提供等に努め、将来的な社会的自立を支援するとともに、新たにスクールカウンセラーを市町の教育支援センター等へ追加配置するなど、教育相談体制の充実を図ってまいります。 さらに、市町や民間団体等と連携した、共家事・共育ての促進に加え、ひとり親世帯における実態把握調査を実施するなど、子どもと向き合う時間、いわゆる「こども時間」の充実・確保のための取組を推進してまいります。
(安心して結婚、妊娠・出産、子育てできる環境の整備)県民が希望どおりに安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる社会を実現するには、結婚から子育てまでの一貫した支援と環境の整備が必要であると考えております。 そのため、結婚支援について、企業や団体の主体的な取組を促進しながら、若い世代の意識醸成に向け、ライフデザインに関する情報発信や研修等を実施するほか、県民のニーズを踏まえた支援のあり方を検討してまいります。 また、産後ケアを希望するすべての方々が安心して利用できるように、利用者と施設間のマッチング機能等を備えたアプリを導入するほか、希望する施設を県内どこでも利用できる仕組みを構築してまいります。 さらに、子育て環境を整えるために必要な保育人材の安定的な確保に向け、新たに、若年層への幼児教育・保育の現場の魅力発信や、DX・ICT化による保育現場の負担軽減を図る取組等を推進してまいります。 併せて、子育ての悩みや体験について語り合う機会を、保護者や地域住民、企業、各種団体の関係者に提供し、地域ぐるみで子育てを応援する人材を育成してまいります。
(教育環境の充実と教育を支える人材の確保)子どもたち一人ひとりの個性に対応した質の高い教育や社会の変化に対応した学びを推進していくためには、多様な学びの場の提供や、教育環境の充実のほか、教育を支える人材の確保が必要であると考えております。 そのため、「長崎県遠隔教育センター」を令和7年度から設置し、地理的条件にかかわらず、遠隔授業やメタバースの活用などにより、子どもたちの興味や関心、進路希望等に応じた多様で豊かな学びを提供してまいります。 また、高校生の外国語教育において様々な学習機会を設け、これからの社会において求められる、異なる言語や文化、価値への理解、コミュニケーション能力の向上などを図り、グローバル人材の育成を推進してまいります。 さらに、地域子ども教室などにおいて、地域における子どもたちの文化芸術活動の場を増やし、将来にわたり親しめる環境づくりを推進するほか、各学校が所蔵する埋蔵文化財を教材として整理・活用し、理解を深めることで、郷土を愛する人材の育成につなげてまいります。 併せて、学校及び地域、家庭、競技団体、プロスポーツクラブ等と連携し、スポーツ体験会など、多様な人材を活用した事業を一体的に展開することで、子どもたちの「健やかな身体」づくり等を推進してまいります。 このほか、学校における働き方改革の観点から、業務支援員の配置やデジタル採点システムの活用拡大、モデル校における実践研究など教員の業務負担軽減につながる取組を促進し、教育を支える人材の確保に努めてまいります。
2.戦略的なブランディングによる国内外の多方面から「選ばれる長崎県」の実現
(多様な地域資源等を活用した交流人口・関係人口の拡大)
交流人口や関係人口を拡大し、県内はもとより国内外の多方面から選ばれる長崎県を目指していくためには、自然・歴史・文化・環境など本県の多彩な魅力や、そのポテンシャルを活かし、県民の皆様が共感するようなブランディング戦略が必要であると考えております。 そのため、現在、幅広い世代の方々に関わっていただきながら、新しい戦略の策定を進めており、まずは、県民の皆様に長崎県の魅力を再認識していただくためのインナーブランディングに取り組み、本県の総体的なイメージ向上につながる「長崎ブランド」の構築に力を注いでまいります。 また、ビジョンに掲げるマニアの聖地化を目指し、新たに、本県が舞台となったアニメ作品を活用した周遊観光を促進するほか、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」を活用した魅力発信等に、市町や民間企業等と連携し、取り組んでまいります。 さらに、関係人口拡大のため、今年度実施した国内外のノマドワーカーに関する調査結果に基づき、ハブ人材の育成等による受入れ基盤づくりのほか、モニターツアーの実施や、イベント出展等によるプロモーションなどにより、デジタルノマドの誘致を推進してまいります。 このほか、日本遺産「国境の島」認定10周年を契機に、関係市町において講演会や周遊イベント等を実施し、さらなる認知度向上や誘客促進を図るとともに、県内のインフラ施設を魅力ある観光コンテンツとして活用してまいります。 併せて、市町や関係団体等による地域資源を活かした観光まちづくりの取組を、県や観光連盟の専門人材が企画段階から伴走支援するとともに、本県へのさらなる移住促進に向け、県の支援サイト「ながさき移住ナビ」のアクセス増加のためのコンテンツ等の改善や、市町への好事例の紹介等の充実を図ってまいります。
(インバウンド誘客の拡大と友好交流・平和発信の促進)海外との交流拡大を図るためには、豊富な観光資源など本県ならではの強みを活かしたインバウンド対策の強化、各種周年事業等による友好交流や平和発信の促進などに取り組むことが重要であると考えております。 そのため、長崎空港と上海・ソウルを結ぶ2つの国際定期航空路線の利用促進に加え、現地説明会の開催などによる新規路線の誘致に取り組むとともに、新たに、海外のOTAサイトを活用した、本県の観光や食、宿泊などの総合的な情報発信による効果的なプロモーションを実施し、海外との交流拡大を図ってまいります。 また、日韓国交正常化60年、中華人民共和国駐長崎総領事館開設40周年などを契機として、本県と海外友好都市との交流関係や人的ネットワーク等の充実を図るほか、在日大使館や総領事館等と連携し、幅広い分野でのさらなる友好交流に取り組み、海外における本県のプレゼンス向上を目指してまいります。 さらに、被爆80年の節目の年にあたり、長崎市や広島県、関係団体等と連携し、被爆地から世界に向けた平和発信を推進するとともに、次代を担う平和人材の育成に加え、地域や世代を超えた平和教育に取り組むことにより、平和意識の醸成を促進してまいります。 なお、去る1月28日に、広島県とともに、国に対し、核兵器禁止条約への署名・批准及びオブザーバー参加を要望してまいりました。今回は残念ながらオブザーバー参加しないことが発表されましたが、唯一の被爆国である我が国が、本条約に署名・批准することは、核兵器廃絶に向けた国際的な機運のさらなる向上につながるものであると考えております。 今後とも、「長崎を最後の被爆地に」という強い思いのもと、核兵器のない世界の実現に向けて力を注いでまいります。
(本県の豊かな食の魅力発信と賑わいの創出)本県のグルメを食した人が笑顔になる「美味しい!長崎」の実現につなげるためには、地域の豊かな農産物や水産物など、県内の豊富な食材等の魅力発信に加え、食の賑わい創出や国内外における販路拡大を促進していくことが重要であると考えております。 そのため、今年度実施中の調査内容を踏まえ、県民や観光客など誰もが本県の食を味わえる「食の賑わいの場」の創出に向け、拠点づくりの具体的な実証や、長崎ならではの食文化の発信等に取り組んでまいります。 また、県産品の輸出拡大を図るため、部局横断的に連携し、長崎和牛や鮮魚、養殖マグロなどについて、東南アジアを中心とした販売プロモーションや新たな販路開拓等を実施してまいります。 加えて、本県のさらなる認知度向上を図り、県産品を実際に購買していただくための環境整備として、新たに民間のECサイト上に県の特設サイトを開設するほか、各サイトへのアクセス情報などを分析するデジタルマーケティングの手法を活用し、効果的な魅力発信等を展開してまいります。
(大型イベント等を通じた交流拡大の推進)令和7年度は、県内外で大型イベントが予定されており、開催を契機とした交流人口の拡大等に積極的に取り組んでまいります。 「ながさきピース文化祭2025」については、地域文化発信事業や障害者交流事業など185事業を実施予定であり、出演者や来場者、その他関係者等含め約190万人の参加が見込まれております。 本年9月の開催までいよいよ7か月となり、市町や関係団体等とともに着実に準備を進めてまいります。 また、開催に合わせ、県では、開幕日の9月14日から、県美術館において「皇居三の丸尚蔵館収蔵品展」を開催し、国宝「蒙古襲来絵詞」など、本県ゆかりの収蔵品の数々を展示する予定としており、県内外の多くの皆様に、貴重な作品に触れていただきたいと考えております。 さらに、本年10月に開催される、「ツール・ド・九州2025」の佐世保クリテリウムについても、佐世保市や関係団体と連携しながら準備を進めており、明日22日には、させぼ五番街において、大会のキックオフイベントを開催することとしております。 今後も、PRイベントの実施等、様々な周知啓発を図りながら、大会開催に向けた機運の一層の向上に努めてまいります。 一方、本年4月から10月までの半年間、「大阪・関西万博」が開催されます。県としても、全国及び海外から多くの人々が集まるこの機会を捉え、本県の魅力を効果的にPRしてまいります。 具体的には、9月に、九州7県の合同により観光や物産等を発信するブースを設置するほか、当催事に連続する形で、関西の主要商業施設等において、本県独自の観光物産等のPRや西九州新幹線の魅力発信等を実施するなど、年間を通じ、関西エリアにおける本県のさらなる認知度向上に向けた取組を、部局連携により、積極的に展開してまいりたいと考えております。 このほか、プロスポーツクラブV・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカとの連携や、長崎スタジアムシティ等の活用により、スポーツ振興や県民のシビックプライド醸成に資する取組を促進するほか、令和8年1月に開催予定のBリーグオールスターゲームの機運醸成や来県されるブースターへのおもてなし等を実施してまいります。
3.最先端のテクノロジー活用やイノベーションによる力強い産業の実現
(新たな基幹産業の育成、新技術の社会実装とチャレンジの促進)本県が有するポテンシャルや産業構造の変化を捉え、新たな基幹産業の育成や、未来を創るサービスの創出、先端技術の社会実装を進めるとともに、様々なチャレンジができる環境整備・仕組みづくりを通して、県全体の産業振興を図っていくことが必要であると考えております。 こうした中、半導体分野においては、関連産業の需要を県内に取り込むため、今般、令和12年度に売上高1兆206億円を達成することを目標とする「長崎県半導体産業成長戦略」を策定したところであります。 令和7年度は、当戦略に基づき、大手半導体関連企業からの受注獲得に向けて、県内企業の設備投資や技術力向上、人材確保にかかる取組等を支援してまいります。 さらに、世界的な需要拡大に伴い、さらなる成長が見込まれる航空機関連産業においては、販路拡大や技術力向上の支援等により、基幹産業としての育成を促進してまいります。 併せて、造船・プラント関連産業や海洋エネルギー関連産業などの成長分野に加え、新たに水素関連産業について、サプライチェーンの構築に資する企業間連携等の取組を支援してまいります。 また、県内企業のサイバーセキュリティ分野等での事業化を目指し、大手セキュリティ企業と県内企業とのマッチングや、共創による新事業展開を支援してまいります。 このほか、スタートアップの推進については、投資家とのマッチングイベントである「ミライ企業Nagasaki」の充実を図るため、新たに首都圏の交流拠点等と連携し、県外から起業家を呼び込むほか、大企業等との取引拡大に向けた支援を実施してまいります。 一方、イノベーション分野では、国家戦略特区である「新技術実装連携“絆”特区」の指定を契機に、ドローンの活用による地域課題への対応を加速させるべく、民間事業者による有人地帯での目視外飛行等の実証調査の推進に加え、ドローンへの理解を深めるためのイベントの開催や、オペレーター育成及びサービス実装に向けた取組の支援等に力を注いでまいります。 また、県内における自動運転バスの社会実装に向け、「長崎空港〜新大村駅」間において実証運行等を推進してまいります。
(持続可能な農林水産業の推進)本県の基幹産業である第一次産業の振興を図るためには、近年の猛暑などの異常気象や激甚化・頻発化する自然災害等に対応した産地づくり、スマート技術の活用による生産性向上や規模拡大、農山村や漁村集落の活性化など、持続可能な農林水産業の実現に資する関連施策を積極的に講じていく必要があると考えております。 そのため、農業分野において、高温や長雨などの気候変動リスクに対応した新たな品種や生産技術等の開発・実証、資機材の導入支援により、気候変動に強い産地づくりを推進するほか、直売所の機能強化や集落における産品づくりの支援等に取り組んでまいります。 また、人口減少や高齢化が進む中、草刈等の集落保全活動やドローンを活用した防除作業をサービス事業体に委託する等の取組を支援し、集落や産地の維持・活性化を図ってまいります。 さらに、畜産業において、繁殖能力の高い雌牛及び種豚の導入や、飼料コストの低減につながるICTを活用した新たな放牧の取組を支援するほか、林業における、県産材を使用した非住宅建築物の木造・木質化を推進してまいります。 一方、水産業については、近年頻発する赤潮への対応など、養殖業における課題解決に向けて、民間のアイデアを活用した技術開発・実証を継続してまいります。 加えて、新たに産地における中核的な養殖業者による先端技術の導入や販売力強化、産地の発展に向けた漁場の有効利用等を支援し、持続可能な養殖産地の育成に努めてまいります。 さらに、離島漁業の活性化を図るため、漁場の生産力の向上や漁業の再生に関する取組を支援するほか、漁業就業者の確保に向け、新規就業者へのリースによる漁船等取得や、漁業集落の雇用創出活動などの支援、移住や漁業就業に関する情報発信等による子育て世代等の呼び込み、スムーズな技術習得等による受入体制づくりを推進してまいります。
(各分野における産業人材等の育成・確保)県内においても人材不足が顕在化する中、DX推進による生産性向上を図りながら、キャリア教育やリ・スキリングの推進、受入環境の整備等により、産業面における人材の育成・確保を図っていく必要があると考えております。 そのため、県内自治体におけるデジタル化・DX施策の推進に向け、県と市町が共同で外部デジタル人材を活用できる体制を構築するほか、ITスキルの活用や就職支援セミナー等のリカレント支援により、県内求職者の就労促進や非正規雇用者のキャリアアップを図ってまいります。 また、大学や産業界等と連携して、専門的な講座や企業見学、高校生アプリ開発コンテストを実施し、アントレプレナーシップ教育を充実するほか、観光を担う人材の育成・確保のため、商業高校と連携したカリキュラムの作成や宿泊施設での体験学習等に取り組んでまいります。 さらに、県内就職を促進するために、高校生や保護者に対して、県内企業の魅力を伝える取組を推進するほか、大学生に対しては、県内大学等との連携による企業交流イベントやインターンシップ等の充実により、学生と企業との交流機会等の拡大を図ってまいります。 加えて、技能者を育成する高等技術専門校における魅力発信の強化や、技能者のスキルアップ及び育成に向けた支援を実施することで、製造業をはじめとする県内企業の人材育成・確保につなげてまいります。 一方、外国人材の活用については、市町や業界団体とも連携しながら、各分野のニーズに応じた効果的な対策をパッケージで講じてまいります。 具体的には、事業者向けの総合相談窓口の設置や、受入促進セミナーの開催、市町と連携した受入環境整備への支援等により、外国人材の受入・定着を促進してまいります。 併せて、IT人材のバングラデシュからの受入や、宿泊施設における海外の大学からのインターンシップを支援するとともに、留学生の県内就職を促進するなど、幅広い業種における外国人材の育成・確保に努めてまいります。 このほか、受入環境の整備を図るため、介護分野において、人材の育成を包括的に支援する「外国人介護人材育成支援センター(仮称)」の開設や、生活面の支援等を実施するほか、農業分野においては、JAなどによる居住環境の改善等を支援してまいります。
4.全世代が豊かで安全・安心に暮らせる持続可能な社会の実現
(適切な医療・福祉・介護サービスや支援を受けられる環境の整備・充実)全世代の県民の皆様が、住み慣れた地域で安全・安心に暮らしていくためには、医療・福祉・介護サービスなどにおける体制の整備や人材の確保など、適切な環境づくりが重要であると考えております。 のため、医療分野については、常勤医師が在籍していない離島公立診療所におけるICTの活用や普及拡大に関して、課題等の解決策を探るための協議会の設置に加え、オンライン診療にかかる体制構築をモデル的に支援するほか、現行のドクターヘリに加え、新たに長崎県病院企業団の離島等医療連携ヘリ(RIMCAS(リムキャス))を非運航日にドクターヘリとして活用することにより、救急患者搬送体制を強化してまいります。 また、発達障害の診療等に取り組もうとする地域の小児科医等に対し、必要な研修等を実施し、診療が可能な医師として認定することで、発達障害児の早期診療や早期療育を促進するほか、透析患者の負担軽減に向け、低所得者の通院にかかる費用の一部を支援する制度を新たに構築してまいります。 さらに、医療人材の確保については、専門医の育成等を行う医療機関における医師の労働時間短縮に向けた、業務のタスクシフト等に要する経費の支援や、看護師等の養成及び県内就職を促進するため、医師会が設置する看護師等養成所の運営にかかる支援の充実を図るほか、不足する病院薬剤師や離島の歯科衛生士の確保に向け、新たに県独自の奨学金返済支援制度を創設することとしております。 一方、福祉分野においては、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を踏まえた「新しい認知症観」の普及啓発を進め、国の基本計画に沿った県計画の策定に向けて調査等を実施するほか、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 に基づく支援体制の構築等により、DVや性被害等の問題に直面する女性を支援してまいります。 また、介護施設において、デジタル化を推進するための機器導入やDX化促進の支援等により、業務や経営の効率化を図り、質の高い介護サービスの提供を実現してまいります。
(誰もが健康で自分らしく暮らすことのできる社会づくりの推進)一人ひとりが持つ多様な価値観や個性が尊重され、誰もが健康で自分らしく暮らしていくための社会づくりのために、健康寿命の延伸に向けた取組や、性別及び年齢、国籍、障害の有無などに関わらず、多様性を発揮できるダイバーシティ社会実現を推進することが重要だと考えております。 そのため、累計ダウンロード数が7万件を超え、順調に利用者数を増やしている、ながさき健康づくりアプリ「歩こーで!」の一層の活用などにより、県民の主体的な健康づくりを促進するほか、県や市町、関係団体、民間事業者、大学等のネットワークを活用し、県民の食に関する理解促進や健全な食生活を実践する食育活動を展開してまいります。 また、高齢者の社会参加促進に向け、市町との共催によるセミナーや地域貢献活動の実践講座を開催するほか、多文化共生社会の実現に向け、これまでの外国人相談窓口の設置や日本語ボランティアの育成に加え、基礎的な講座や対話型の学習など、様々なレベルでの日本語教育の充実を図ってまいります。 さらに、官民で組織する「ながさき女性活躍推進会議」と引き続き連携しながら、企業経営者等の意識改革や、管理職登用に向けた女性人材の育成を支援するとともに、市町や民間団体等と連携した啓発等により共家事・共育てを促進し、女性活躍を推進してまいります。 このほか、人と動物が共生できる住みよい社会づくりの実現を目指し、地域猫活動に係る野良猫の不妊化手術支援や、動物愛護についての学習及び啓発、動物愛護管理センター(仮称)の建設など、動物愛護推進や動物殺処分ゼロに向けた施策を実施してまいります。
(県民の安全・安心を守る社会基盤の整備と脱炭素社会の実現)県民の皆様の安全・安心を守るため、能登半島地震の課題等を踏まえた防災対策を強化するとともに、強靱な県土づくりをさらに推進していく必要があると考えております。 そのため、防災対策の充実・強化として、今年度の予備調査を踏まえた海域活断層に係る詳細調査や、過去に行った本土地区等の活断層調査の見直しにより、地震アセスメントを実施するほか、防災タイムラインの策定や防災訓練の強化などに取り組んでまいります。 併せて、国の交付金を活用し、トイレカーの導入や避難所の生活環境改善にかかる資材の備蓄、災害時における孤立地域対策のためのヘリコプターの離発着にかかる適地調査等を速やかに実施してまいります。 さらに、消防団員の確保に向けた女性・若者の加入促進に向けた取組や消防団の組織強化、自主防災組織の結成並びに活動の活性化を支援してまいります。 このほか、激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命・財産・暮らしを守り支えるため、5年間延長された国の緊急浚渫推進事業債などの有利な財源も活用しながら、強靱な県土づくりを推進してまいります。 一方、2050年の脱炭素社会の実現に向けた対応についても着実に実施していくことが求められております。 県民や事業者、行政などそれぞれの主体による、省エネ・再エネ等の取組を推進するほか、環境への負荷を低減し、ごみのない循環型社会を目指すため、市町と連携し、廃棄物の減量化や再資源化に向けた啓発活動等に取り組んでまいります。
5.現下の社会経済情勢を踏まえた諸課題への対応
(物価高騰対策へのきめ細やかな対応)長引く物価高騰により影響を受けている県民の皆様や事業者・生産者の方々に対し、国の交付金を活用しながら、引き続き、必要な支援をしっかりと講じてまいりたいと考えております。 具体的には、生活者向けの支援として、子育て世帯の家計負担軽減のため、学校給食費等の一部を支援するとともに、県民生活の下支えや事業者等の売上拡大に向け、市町と連携し、デジタル技術等も活用したプレミアム商品券の発行等に取り組んでまいります。 また、事業者向けの支援については、農林水産業への取組として、燃油や肥料等の使用量低減に向けた機器等の導入や、節電効果の高い機器への交換、養殖経営に必要な資材の購入等を支援するほか、長崎和牛の消費拡大に向けた販売促進キャンペーンを展開してまいります。 さらに、県内中小企業等のデジタル人材育成や生産性向上のための設備等の導入を支援するほか、経営面について、事業承継の取組や各種補助金等の申請支援、適切な価格転嫁に向けたサポート等を実施してまいります。 このほか、県内製造業者が行う生産性向上のための設備投資や、公共交通事業者の経営効率化やインバウンド受入等に資するデジタル化の取組を支援してまいります。
(地域コミュニティを支える中小事業者等に対する支援)人口減少・少子高齢化の進展等に伴う地域経済の活力低下や人手不足等への対策として、中小・小規模事業者等のデジタル化等を推進し、生産性向上や賃上げ等につなげていく必要があると考えております。 そのため、商工団体と連携し、伴走支援等による経営指導の強化を図ることにより、小規模事業者のデジタル化や事業承継等を支援してまいります。 また、中小の食料品製造事業者が、原材料価格等が高騰する中においても、利益を確保し、賃上げにつなげていけるよう、生産性向上や収益拡大に向けた商品開発等の取組を支援してまいります。 さらに、地場産業等の成長促進のため、離島地域に加え、新たに本土の条件不利地域等で生産・加工された産品の販路拡大や、生産者・事業者の商品開発及び生産拡大等を伴走型で支援してまいります。 このほか、地域コミュニティの核となる商店街の再生のために、市町と連携し、こどもの居場所づくりなど、地域課題の解決等につながる商店街の取組を支援してまいります。
(離島・半島地域の振興、地域公共交通の維持・確保)本年3月末で期限を迎える半島振興法の改正・延長については、国等の関係機関に対し、半島地域における、能登半島地震を踏まえた防災・減災対策の充実や、高規格道路をはじめとする道路整備の促進などについて、積極的に要望活動を行ってまいりました。 県としては、引き続き、半島振興法の改正・延長の動向を注視しながら、関係市町等とも連携し、半島地域の自立的発展に向けて取り組んでまいります。 一方、令和9年3月末に期限を迎える有人国境離島法については、私自身が離島出身であることから、この法律のありがたさを機会あるごとに実感し、本県にとって欠かせないものと強く認識しております。 そのため、令和7年度においては、法の改正・延長に向けて、有人国境離島地域の保全及び地域社会の維持に支障が生じることのないよう、国への働きかけを強化するとともに、関係自治体と連携し、県選出国会議員や関係団体等の皆様にもご協力いただきながら、航路・航空路運賃低廉化の対象者の拡大や、雇用機会拡充につながる対策の強化などを要望してまいります。 また、離島地域の認知度向上や優良事業の創出を図るため、しまのビジネスコンテストを開催するほか、住民の安全・安心や地域活性化に寄与する海上高速交通の維持・確保のため、老朽化した高速船ジェットフォイルの更新にかかる支援を継続してまいります。 このほか、持続可能な地域公共交通ネットワークの構築に向け、県内交通事業者等による人材確保の取組や、市町におけるコミュニティ交通への転換を支援してまいります。
(IRの取組等を活かした県北地域の振興)IRの取組で目指してきた交流人口拡大や産業振興、雇用創出などの考え方を継承し、その知見や地域資源を活かして、県北地域の振興を図ることが重要であると認識しております。 そのため、ハウステンボスを中心とした広域周遊観光や、西海橋公園などの地域資源を活かした観光拠点整備等により、観光振興を促進するほか、「ツール・ド・九州2025」の開催や、大会を契機とした県内のサイクルツーリズム推進等による地域の振興に取り組んでまいります。 また、カーボンニュートラルに向けたGX関連施策や工業団地整備、企業誘致などの産業基盤の充実・強化等により産業振興を促進してまいります。 県としては、こうした取組を市町や民間団体等とも連携しながら推進し、県北地域の活性化はもとより、その効果を県全体へと拡大してまいりたいと考えております。 それでは次に、その他の主な施策や懸案事項などについてご報告を申し上げます。
九州新幹線西九州ルートの整備促進
九州新幹線西九州ルートについては、新鳥栖〜武雄温泉間の整備において、佐賀県が指摘する地方負担や在来線の在り方などが課題となっております。 一方、既に開業した長崎〜武雄温泉間においては、人流が活性化し、まちづくりが進展するなどの具体的な効果が現れていることから、全線フル規格による整備への一層の気運醸成が重要であると考えております。 そのような中、去る12月16日、県内経済団体の主催による「九州新幹線西九州ルート整備促進シンポジウム2024」が長崎市で開催されました。 当日は、県内各地や佐賀県などから約1千人の参加があり、基調講演では、全線フル規格で整備されることで、我が国の国土軸へ組み込まれる将来性が示されたほか、県内外の観光やまちづくりの専門家によるパネルディスカッションが行われるなど、西九州地域の将来の発展に向けて気運が高まったものと考えております。 また、私自身、2月4日、徳永県議会議長や沿線三市の関係皆様とともに、自民党の森山幹事長をはじめ、政府・与党に対し、課題解決に向けた具体策の提示や国を交えた関係者間での協議の実施などを強く要望してまいりました。 県としては、今後、関西直通運行の必要性について、県内外への情報発信を強化し、さらなる気運醸成を図るとともに、引き続き、政府・与党をはじめ関係者に対して、議論の進展や地域課題の解決について働きかけるなど、全線フル規格による整備の早期実現に向け、力を尽くしてまいります。
(野生イノシシの豚熱感染確認に伴う防疫対応)
去る2月3日、松浦市福島町において、野生イノシシについては本県で初めてとなる豚熱感染が確認されました。 県では、直ちに私を本部長とする対策本部を設置し、関係機関や庁内関係部局と今後の対応について確認を行うとともに、養豚関係者を対象に長崎県豚熱防疫対策会議を開催し、防疫対策の徹底を図りました。 具体的な対策としては、ウイルスの拡散防止に向け、国や松浦市、地元猟友会の協力のもと、野生イノシシ用の経口ワクチンを福島町内に散布したことに加え、県内全養豚場に消毒用消石灰を配布し、緊急一斉消毒を行ったところであります。 引き続き、市町や関係団体等の皆様と十分連携を図りながら、最大限の危機意識を持って、的確な防疫対策を実施し、養豚場での豚熱の発生防止に全力を注いでまいります。
長崎大学BSL4施設の大臣指定
去る1月24日、長崎大学の高度感染症研究センター実験棟(BSL4施設)が、厚生労働大臣から感染症法に基づく特定一種病原体等所持施設に指定されました。 この指定により、危険度の高い病原体である特定一種病原体を研究目的で扱うことのできる日本初の施設となり、厚生労働省の監督の下、これまで行えなかった高度な研究が可能となることから、同病原体に関する研究や人材育成がさらに進むものと期待しております。 県としては、平成27年に長崎大学と長崎市の三者で締結した、「感染症研究拠点整備に関する基本協定」に基づき、三者連絡協議会や、地域住民の代表等を委員に加えた地域連絡協議会に参画し、運用状況や安全対策について協議を重ねてまいりました。 引き続き、長崎大学に対し、同施設の安全性の確保等について、適切な運用を要請してまいります。
石木ダムの推進
石木ダムについては、渇水や洪水などの自然災害から地域の皆様の安全・安心の確保を図るうえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があります。 昨年の事業再評価において、完成工期を令和14年度まで延長することとなりましたが、工期内の確実な完成に向け、新たな工程に沿って着実に工事を進めてまいります。 一方、川原地区にお住まいの13世帯の皆様のご理解とご協力を得たうえで、事業を円滑に進めることが最善であるという考えにも変わりはなく、引き続き話合いの機会をいただけるよう努力を重ねてまいります。 また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進めております水源地域整備計画については、昨年12月に素案の公表を行い、現在、地元川棚町の皆様を中心に、広くご意見を伺っているところであり、計画の早期策定に努めてまいります。 県としては、石木ダムの一日も早い完成に向けて、引き続き、佐世保市及び川棚町と一体となって、事業の推進に力を注いでまいります。
安全・安心な県土づくりの推進
県では、産業の振興や、交流人口の拡大による地域の活性化、安全・安心かつ強靱な県土づくりに向けて、高規格道路の整備を重点的に進めております。 このうち、西九州自動車道については、佐々インターチェンジから佐世保中央インターチェンジ間の4車線化工事が、3月23日に完成予定となっているほか、松浦インターチェンジから平戸インターチェンジ間も、来年度中の完成供用が予定されております。 こうした道路網の整備促進により、安全性・走行性の向上や災害時の代替機能の強化、地域活性化等が図られるものと期待しているところであり、引き続き、幹線道路ネットワークの整備を推進してまいります。 また、去る2月2日、国の直轄事業である本明川ダムについて、徳永県議会議長をはじめ多くの関係皆様にご出席いただき、本体工事着工式を国や諫早市とともに開催いたしました。 当ダムは、これまで数多くの洪水被害を出している本明川の治水対策と渇水時の河川環境の維持を目的として整備され、令和14年度の完成見込みとなっております。 このたびの工事着工にあたり、ダム事業にご理解とご協力いただきました地権者や地元関係者の皆様、並びに事業推進に向けご尽力いただきました本県選出国会議員や県議会、関係団体の皆様に、改めて心から感謝を申し上げます。 県としては、ダム周辺の県道や河川公園の整備等を計画しており、今後とも、ダムの早期完成と周辺の環境整備等について、国や諫早市と一体となって取り組んでまいります。
企業誘致の推進
去る12月26日、大阪府に本社を置くフォルテック株式会社が、佐世保市への立地を決定されました。同社は、生産設備の自動化やシステム開発を実施されており、5年間で20名を雇用し、自動車シートカバーの縫製工程の自動化や縫製技術のシステム化に向けた開発などを行うこととされております。 また、1月27日には、東京都に本社を置く株式会社ウイズ・ワンが、長崎市への立地を決定されました。同社は、大手電機メーカーなど法人向けのWebアプリケーション開発やシステム構築を実施されており、5年間で37名を雇用し、東京本社で行っている業務の一部やAIを活用したシステム開発を行うこととされております。 県としては、雇用の拡大と地域経済の活性化を目指して、地元自治体や関係機関と連携しながら、企業誘致の推進に力を注いでまいります。
文化の振興と文化財の動向
去る12月20日、長崎県美術館に対し、フィデル・センダゴルタ駐日スペイン大使から、大変名誉ある「スペイン文民功労勲章」の「名誉の楯」を授与いただきました。 この勲章は、スペイン王国への傑出した貢献が認められた個人・団体に対し、フェリペ6世 スペイン王国国王陛下から授与されるものであります。 長崎県美術館は、2004年にスペイン国立プラド美術館と友好促進に関する覚書を締結し、作品研究や学芸員研修などの絶え間ない交流を続け、現在では東洋有数の規模を誇るスペイン美術コレクションを常設展示しております。それらの功績が認められ、国内の美術館では初となる受章となりました。 本年は、開館20周年を迎えるとともに、被爆80年の節目にもあたることから、プラド美術館所蔵のゴヤの油彩画を展示するなど、戦争をテーマとする企画展を実施する予定としております。 県としては、今後も、県美術館を通して、県民の皆様に、一流の芸術文化を体感いただくための機会を創出してまいります。 一方、平成24年10月に盗難され韓国に持ち出されていた対馬市の県指定有形文化財「観音寺の観世音菩薩坐像」について、1月24日に、韓国の大田(テジョン)地方検察庁から観音寺への返還手続きがなされ、現在、法要のため同国の浮石寺(ふせきじ)へ貸し出されているところであります。 県としても、関係皆様のご尽力により、仏像が返還手続きにまで至ったことは大変喜ばしく、引き続き、国や対馬市等と連携し、仏像が無事に観音寺に戻るまで、適切に対応してまいります。
スポーツの振興
去る2月15日、サッカーJ2リーグの2025シーズンが開幕し、V・ファーレン長崎は新たなスタートを切りました。 昨シーズンは、惜しくもJ1復帰は叶いませんでしたが、今シーズンこそは、選手やスタッフ、サポーターが一体となって、悲願のJ1昇格に向けて突き進んで行かれることを期待しております。 また、長崎ヴェルカは、現在、男子プロバスケットボールリーグB1において奮闘されており、今シーズンの目標としているチャンピオンシップ進出を目指して、勝ち星を重ねられることを願っております。 県としても、県民応援フェアの開催等によりホームゲームを盛り上げるなど、市町や関係団体、県民の皆様と一体となって、両チームを後押ししてまいります。 一方、3月に開催される「第97回選抜高等学校野球大会」の21世紀枠による出場校として、壱岐高校が本県では初めて選出されました。 今回の選出は、全国の離島地域の高校球児達に勇気を与えるものであり、同校野球部の選手・指導者の方々をはじめ関係者の皆様方に、改めて、お祝いを申し上げますとともに、憧れの阪神甲子園球場において、日頃の練習の成果を発揮され、はつらつとプレーされることを期待しております。 また、昨年12月に東京都で開催された「令和6年度天皇杯全日本レスリング選手権大会」において、本県出身の吉武まひろ選手が女子68kg級で準優勝を果たしました。 さらに、1月に開催された「2025年ベルギー国際柔道大会」において、長崎明誠高校3年の近藤杏樹選手がジュニアの部女子48kg級で優勝を飾りました。 選手並びに関係者の皆様のご健闘を心からたたえるとともに、今後とも、本県スポーツの振興と競技力の向上に力を注いでまいります。
次に、議案関係についてご説明いたします。 まず、令和7年度の当初予算については、先の11月定例会での長崎県の主要施策素案に対する議論や、政策評価の結果等を踏まえて編成いたしております。 一般会計の予算額は、 7,347億3,620万9千円 特別会計の予算額は、 2,340億1,248万4千円 企業会計の収益的支出及び資本的支出の総額は、 104億1,350万6千円 となっております。 次に、令和6年度補正予算については、国の経済対策補正予算への対応に要する経費、給与の改定等に要する経費、国庫支出金の決定等に伴う事業費の増減、その他年度内に執行を要する緊急的な事業費等について計上いたしました。 一般会計 137億5,334万 円の減額 特別会計 41億7,804万6千円の減額 企業会計 1億 128万4千円の減額 補正をしております。 この結果、令和6年度の一般会計の累計予算額は、 7,690億7,740万4千円 となっております。 次に、予算以外の議案のうち、主なものについてご説明いたします。 第21号議案「長崎県こども・女性・障害者支援センター設置条例の一部を改正する条例」は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所機能について、所管区域を変更するため、所要の改正をしようとするものであります。 第24号議案「長崎県こども未来応援基金条例」は、子どもが主役の安全・安心でチャレンジできる「こども場所」の充実をはじめとした、子ども施策を実現していくため、新たに基金を設置しようとするものであります。 第42号議案「契約の締結の一部変更について」は、川口アパート建替事業について、請負契約を一部変更しようとするものであります。 第46号議案は、海区漁業調整委員会の委員の任命について議会の同意を得ようとするものであります。 第65号議案は、長崎県監査委員の選任について議会の同意を得ようとするものであります。 委員といたしまして、 松本 洋介 君 坂本 浩 君 を選任しようとするものであります。 いずれも適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 なお、監査委員を退任されます、大場 博文君、堤 典子君並びに海区漁業調整委員会委員を退任されます皆様には、在任中、多大のご尽力をいただきました。この機会に厚くお礼申し上げます。 その他の案件については、説明を省略させていただきますので、ご了承を賜りたいと存じます。 以上をもちまして、本日提出いたしました議案の説明を終わります。 なにとぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。