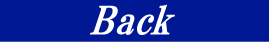主な質問・質疑
各常任委員会の委員長報告要旨については、こちらをクリックしてください。
![]()
<審査案件>
議案:第88号議案「平成20年度長崎県一般会計補正予算(第1号)」のうち関係部分 ほか8件
<審査結果>
議案:第92号議案 修正のうえ可決
その他の議案 原案のとおり可決すべきものと決定
| 議案にかかる主な論議 | |
|---|---|
(修正議案) |
「長崎県子育て条例」中の第27条第4項の協議会委員について「子どもや子育て支援について学識経験のある者などから」という表現を「広く県民の中から」との表現に一部修正。 |
(質問) |
長崎県病院企業団の設立に関する協議に関して、企業団設立について、今後の進め方をどう考えているか。 |
(答弁) |
企業団設立について、関係市町では、新上五島町、雲仙市、島原市、対馬市で可決となった。南島原市は10月2日、五島市は10月15日の採決予定である。今後、全ての市町で議案が可決されれば、総務省へ企業団設立の許可申請を行う。また、企業団設立について住民に周知をしていきたい。 |
(意見) |
離島医療圏組合の各病院の見直しにあたっては、地域住民への情報公開、説明・協議を行うこと、病床数については、地域の実情を考慮して病院関係者において十分誠意をもって協議すること、医師等の医療資源確保については、企業団として最大限の努力をすること。 |
(意見) |
公立病院が厳しい経営状況にある中で、効率よい病院経営をするということでの提案である。 |
(意見) |
地域において安定的かつ継続的に医療サービスの提供ができるための改革であるので、住民にも改革の内容を伝えていきながら進めてほしい。 |
(質問) |
つくも苑建て替えの設計費が当初予算に組まれているが、進捗状況はどうか。また今後のスケジュールをどう考えているか。 |
(答弁) |
当初予算は現地建て替えで組んでいるが、市街地移転と現地建て替えの両方の要望があっており、設計は、方針を検討した後となる。建て替えについては、入所者と利用者へのサービスを第一に考え、年内には方針を出したい。 |
(意見) |
双方の意見が成り立つ方法を模索してほしい。 |
| 議案以外の主な論議 | |
(質問) |
療養病床転換計画で、国の療養病床目標値は変更があっているが、本県は計画を見直さなくて不都合は生じないのか。 |
(答弁) |
国は、平成20年度から24年度の『医療費適正化計画』を平成22年度に中間評価として見直しの検討をすることとなっている。本県の療養病床転換計画は『長崎県医療費適正化計画』と整合性を図って策定しており、平成22年度に転換計画の進捗状況を見て、必要な場合は、見直しを検討したい。 |
(意見) |
今年度の転換見込44床に対し、現在の転換数は18床だが、当面このままで進めるのか。現場の意向を聞く中で、進捗管理を行ってもらいたい。 |
(答弁) |
療養病床転換計画については、医療の必要な方にはそのまま療養病床に残っていただき、医療の必要性の低い方は介護保険施設等に入っていただくこととしており、介護難民が生じないようにする。転換が進まないのは、医療機関が診療報酬、介護報酬の改定の状況を見て今後の判断をしようとしているからだと思われる。転換計画は医療・介護の現場の実態を把握しながら進めていきたい。 |
(質問) |
長崎市における高機能病院の設置について、県の関わりはどうなっているのか。また、高機能ということで県の負担は考えられないか。 |
(答弁) |
公立病院改革プラン検討協議会において高機能病院の具体案がないと検討できないとのことで、現在具体案を作成中である。横浜市の例があり、市が高機能病院を設置し、日赤に運営を委託することが考えられる。市の要望があれば、市の範囲を超える救命救急センターや周産期医療センターなどの運営に対する県の負担や、場合によっては県が経営に参画することも考えられる。 |
(質問) |
原材料にメラミンの混入が確認された加工食品について、国からの情報では、小売用については、本県での流通はあってないが、県としても独自に調査を行い、販売の実態がないことを確認したとのことであるが、確認方法は電話での聞き取りによるものか。 |
(答弁) |
小売用は、流通が限られている特定商品なので、県内の流通を把握するため電話での聞き取りを行い、主要小売店舗には流通していないことを把握した。また、通常の食品衛生監視活動の中でも各店舗に入り、確認している。今後、段階的に必要に応じて検査等も視野に入れながら調査をしていく。 なお、業務用は、本県を含む全国の病院、福祉施設等で提供されたが、本県では健康被害の報告は受けていない。 |
(質問) |
ごみの投げ捨て等防止重点地区等の指定について、指定地区の範囲の周知方法とパトロールなどの推進体制の整備について、どのように行っていくのか。 |
(答弁) |
ポスターや看板の設置、定期的なパトロールなどにより周知するとともに、既存の組織の活用や地元の市町、関係団体などで構成する協議会を設けて環境美化に努める。 |
(意見) |
十分に検討し、実施して欲しい。 |
| その他、交わされた論議 | |
|
|