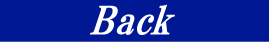定例会等の開催概要
主な質問・質疑
●定例会を終わって ●主な質問・質疑 ●会期日程 ●本会議一般質問 ●意見書・決議 ●議員提案条例
各常任委員会の委員長報告要旨については、こちらをクリックしてください。
![]()
<審査案件>
議案:第142号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」のうち関係部分ほか1件
<審査結果>
議案:原案のとおり可決すべきものと決定
| 議案にかかる主な論議 | |
|---|---|
| (質問) | 公の施設の指定管理者の指定について、選定にあっては、ビジネス支援プラザの目的に合致した能力のある指定管理者の選択が必要だが、申請者の評価はどのように採点したのか。 |
| (答弁) | 今回、4つの評価の観点を設定している。その中の一つである「安定した管理運営」では、経営的に安定しているかという点、また、プラザの設置目的を理解しているか、公の施設として公平な管理運営ができるかなどに細分化し、それぞれの項目を審査会において採点した。 |
| (質問) | 透明性を確保する観点から、評価項目の詳細や結果について極力公表すべきと考えるが、各項目の点数は公表できるか。 |
| (答弁) | 採択されたコンベンションリンケージ以外の申請者の名称を出さない形であれば、各項目の点数を公表できる。 |
| 議案以外の主な論議 | |
| (質問) | 中国からの観光客数は、韓国や台湾などに比べるとまだ少ないが、ビザの解禁等に加え、中国国内における日本の旅行代理店の業務に対する制限が緩和されたというような情報もある。中国からの誘客に力をいれるべきではないか。 |
| (答弁) |
現在、中国内における日本の旅行業者は、日本から中国への旅行者しか取り扱えないが、今後、中国人を対象にした日本への送客ができるようになるとのことである。 個人ビザの解禁により一気に増えることは難しいが、長い歴史の上で長崎県と中国は深い友好関係にある。是非、力を入れて取り組みたい。 |
| (質問) | 北京商談会の具体的な商談実績はどのような状況か。また、予算はどれくらい使っているのか。 |
| (答弁) |
県内からの出展が15社。参加者は110社、380名であった。 具体的な成果については、精査中であるが168件の商談があったと報告されている。 詳しくは、とりまとめ次第報告する。 予算は県全体で5,700万円であるが、そのうち物産関係では3,100万円である。 成果がでるまでには少し時間がかかるが、今まさに、昨年実施した商談の一つ一つがようやく実を結んでいるところである。 |
| (報告) | 「ベンチャー企業等の支援の在り方及びバイオラボ社に係る問題についての法的な対応等に関する意見書」への対応について、詐欺罪による告訴を含む法的な対応については、刑事、民事の両面から責任を問いたいとの考えに立ち、複数の弁護士へ相談したが、詐欺罪の立証が極めて困難であるとのことから、刑事告訴は困難であると考えている。 |
| (意見) |
告訴について、立証が困難な状況では、この結果を受け入れざるを得ない。また、民事による手続きを行うとの報告もあったので、法的な対応については了としたい。 新たなベンチャー支援の在り方については、今後も十分検討し、時期に応じてフレキシブルに対応していただきたい。 |
| (質問) |
地域活力基盤創造交付金を活用した船舶建造等について、交付金の出し方については、地域にきちんと回るように考えるべきではないか。 また、県内中小造船会社が大手造船会社の協力を得るなどして、新船建造の受注が県外へ流れないようにすべきではないか。 |
| (答弁) |
地域活力基盤創造交付金については、10月22日の第3回 離島基幹航路運賃対策協議会において副知事、地域振興部長出席のもと、フェリー運航事業者に対し、県内中小造船業界への発注に配慮するよう要請したところである。 また、中小と大手の協力ということに関しては、大手造船会社にとって規模として魅力があるかどうかという問題や、発注者側のフェリー運航事業者からすれば、設計から建造まで一貫している方が好ましいとの考えもあるのではないか。いずれにしても、県内受注の機会を広げるため、大手造船会社等との連携による受注も含め、どのような方法が可能か、研究したいと考えている。 |
| (質問) | 有明海の種苗放流に係る追跡調査とその放流効果については、どのような状況か。 |
| (答弁) |
代表的な魚種としては、クルマエビ、トラフグがある。クルマエビについては、有明海関係 4県共同での放流の効果調査に取り組み、その結果を受けて放流適地において実施をしている。放流効果を高めるため、今年度から大型サイズの種苗放流を実施していく。 トラフグは、本県単独で年間50万尾の放流を実施しているが、漁獲されたトラフグのうち天然物に対する混獲率は15パーセントから30パーセントで、効果があがっている。 |
| (質問) |
農家戸別所得補償について、来年からはモデル的に米を対象に検討されているとのことだが、地域によって水田作と畑作の面積比に差があり、また、第二種兼業者の割合にも違いがある。 農業者の間には、地方の実情により地域間で不公平となるのではないか、などの不安感が生じている。県はこの制度をどのように把握しているか。 |
| (答弁) |
水稲だけで見れば、そのような部分も生じるかもしれない。国は、平成22年度は米でモデル的に実施し、23年度以降は畜産等も含めて実施の方向である。 米によるモデル事業をしっかり検証し、それを受けて制度設計していくとのことである。よりよい施策に組み立ててもらうよう県としても意見を述べていきたい。 |
| (要望) | 不公平感が生じない、また農業者の意欲が削(そ)がれない制度となるよう、県も国に地域の声を届けて欲しい。 |
| (質問) | 県有種雄牛の凍結精液が紛失した事件について、サブセンターである農協の管理指導も徹底されると思うが、再発防止のためのルールづくりの状況はどのように進められるのか。 |
| (答弁) |
凍結精液の管理については、農協に委託をしていたが、在庫管理に対する調査は書類のみで行っていた。今後は定期的な立入検査の実施や抜き打ち検査を行うこととしている。 新しいルールづくりについては、弁護士や関係機関などからなる検討会を立ち上げ、今年度中に凍結精液の流れを把握する方法や、県外流出した場合の具体的な対応策などを検討していきたい。 |
| (質問) | 諫早湾干拓フォーラムについて、開門反対の長崎の立場を理解してもらうよいチャンスである。諫早湾干拓地の現状などを、しっかりと理解していただけるようなフォーラムであって欲しいが、どのような方々に呼びかけを行っているのか。 |
| (答弁) |
国会議員や県議会議員を始め、県人会、東京懇話会の皆さん、また、日本経済新聞に関係する食品・流通業界の方や、一般の方など幅広く呼びかけている。 現在、六百数十名の参加希望がある。フォーラムの状況は、終了後、日本経済新聞に掲載し、諫早湾干拓地の防災機能や環境保全型農業の状況などを全国に広く発信し、開門反対への理解を訴えていきたい。 |
| その他、交わされた論議 | |
|
|