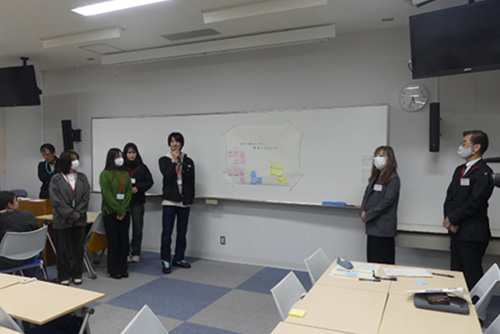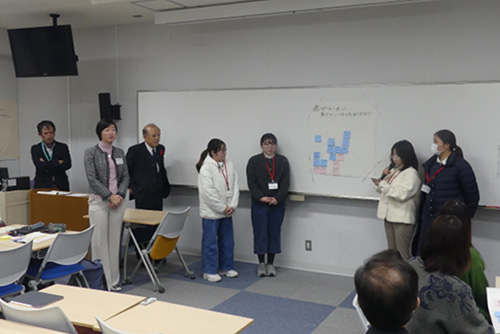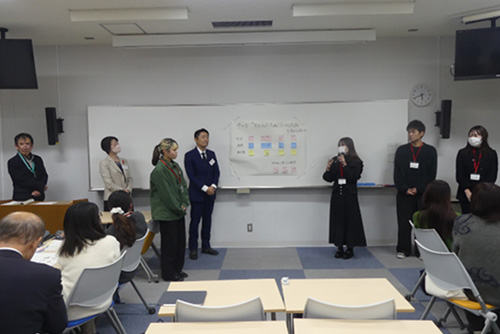長崎県立大学との包括連携協定に基づく事業(令和6年度)
| 項目 | 男女共同参画にかかる意見交換会 |
|---|---|
| 日時 | 令和6年12月17日(火)16時20分~17時50分 |
| 場所 | 長崎県立大学 シーボルト校 中央棟1階M104講義室 |
| 出席者 |
【参加議員】 自由民主党:ごうまなみ議員、改革21:白川鮎美議員、公明党:川崎祥司議員、 県民会議:中山功議員、日本共産党:堀江ひとみ議員、もったいないよ 長崎:大倉聡議員 【参加学生】 国際社会学科 学生12名 |
| 意見 交換の 概要 |
1. 男女共同参画にかかる意見交換の目的説明(川崎祥司議員) ◎意見交換の目的(PDFファイル/62KB)
2. 意見交換
○テーマ:女性が働きやすい環境をつくるには
<Bグループ> ○テーマ:男女が共に働きがいのある社会を目指す
<Cグループ> ○テーマ:男女共同参画に対する意識を高めるためには
3. 各グループによる発表 <Aグループ>
<Bグループ>
<Cグループ>
4. まとめ・感想(各議員)
 ごうまなみ議員  白川鮎美議員  川崎祥司議員 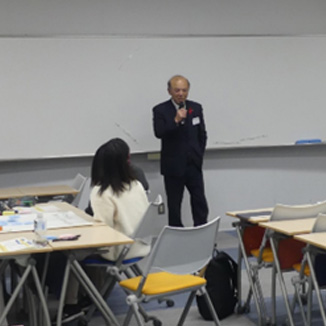 中山功議員  堀江ひとみ議員  大倉聡議員 |
| 項目 | 長崎県立大学における議員講演 |
|---|---|
| 日時 | 令和6年11月21日(木)10時40分~12時10分 |
| 場所 | 長崎県立大学 シーボルト校 中央棟2階M201講義室 |
| 内容 |
演題:「もっと政治を身近に!政治参加のススメ~笑顔で暮らせる長崎県へ~」 演者:饗󠄀庭敦子議員 対象:国際社会学科 学生約40名 |
| 講演の 概要 |
◎講演スライド(PDFファイル/5,979KB)
|
| 項目 | 長崎県立大学における議員講演 |
|---|---|
| 日時 | 令和6年10月8日(火)10時40分~12時10分 |
| 場所 | 長崎県立大学 佐世保校 505教室 |
| 内容 |
演題:「長崎県議会の現状と課題」 演者:冨岡孝介議員 対象:長崎県立大学生 約300名 |
| 講演の 概要 |
◎講演スライド(PDFファイル/7,791KB)
|
| 項目 | インターン生と議員との意見交換 |
|---|---|
| 日時 | 令和6年9月26日(木)16時30分~17時30分 |
| 場所 | 長崎県庁議会棟2階会議室 |
| 出席者 |
【参加議員】 自由民主党:山村健志議員、県民会議:中山功議員 【参加学生】 ・長崎県立大学地域創造学部公共政策学科の学生 1名(インターン生) |
| 意見 交換の 概要 |
1. 学生による意見交換テーマに基づく発表 ◎若者の県外流出について(PDFファイル/352KB)
|