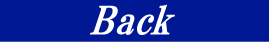過去の定例会情報はこちら
主な質問・質疑
平成15年9月定例会本会議での一般質問の主な内容は次のとおりです。
各常任委員会の委員長報告要旨については、こちらをクリックしてください。
| |
今回示された県の中期財政見通しでは、平成15年度当初予算をベースに試算すると、毎年、100億円から170億円の収支不足が生じる見込みであり、平成20年度末には赤字団体となるおそれがあるという厳しい財政状況に対し、どう対処するのかと質した。
県側の答弁
歳出については、これまでも行政体制の見直しや政策評価による既存事業の見直し、予算編成を通じた施策の重点化を進めてきたが、今後さらに、これらの取り組みを徹底していきたい。
一方、税収が財政運営のカギを握ると考えるが、その増加を図るため、県内経済の活性化が緊急の課題である。今後の予算編成に当たっては、雇用の場の維持・拡大、県内産業の生産性の向上などに結びつくソフト事業への重点配分を行うこととしている。 |
| |
2月の会社更生手続開始の申し立て後、県がこれまで支援してきた施策の効果と、今後、具体的にはどのような支援をしていくのかと質した。
県側の答弁
県は、ハウステンボスが会社更生手続開始の申し立てを行って以来、ハウステンボス支援緊急対策事業を地元佐世保市や県観光連盟などと一体となって展開してきた。
ハウステンボスの分析によると、県等が実施した「十万人の県民がハウステンボスに行こう!」県民運動などにより、入場者の県民比率の約9ポイント増やモーレンクラブ会員の約1万人増、旅行会社4社とのタイアップによる約3万人の送客や、全国紙をはじめとするマスメディアを活用した各種支援などによる集客が図られ、会社価値の劣化を防ぐことができたと評価されている。
県としては、地元佐世保市などと連携を図りながら、旅行会社等とのタイアップによる誘客や、市町村、各種団体に対する入場促進の働きかけなど、ハウステンボスに対する支援を引き続き実施してまいりたい。 |
| |
2003年長崎ゆめ総体は、本県選手団のすばらしい活躍や、高校生「一人一役運動」の成功など、数多くの感動の余韻を残して閉幕したが、本県知事として、この大会をどのように総括しているのかと質した。
県側の答弁
ゆめ総体に臨む高校生の積極性や行動力に対し、心の底から感動を覚えるとともに、高校生の持つ限りない可能性と潜在的な力が本県の将来をたくましく担う力になることを確信した。
伝統芸能を取り入れた公開演技、しま地区での剣道競技の開催、陶磁器による参加章・入賞メダルの製作など、本県の特性を十分に生かした大会とすることができ、本県の魅力を全国に発信できたものと考えている。
競技においても、本県選手団は8つの優勝を含め60の入賞を果たしたことは、中・長期的な展望に立ち、一貫性のある競技力向上対策に努めてきた成果であると考えている。
高校生がこの長崎ゆめ総体の経験を基盤として、さらにたくましく成長してくれることを期待するとともに、今回の取り組みの成果を活力ある長崎県づくりに繋げてまいりたい。 |
| |
食生活の指導・啓発を通じて農業への理解を深める「食育」運動について、次のとおり質した。
1.地場農産物は安心だという県民からの信頼を得るために、生産者に対する具体的な働きかけはどうしているのか。
県側の答弁
農薬適正使用の徹底、出荷段階における自主検査体制の確立、農薬使用実績等の生産履歴の提供などの取り組みを生産者、農業団体と一体となって積極的に推進している。
また、土づくりを通じて、化学肥料及び化学農薬の削減を行うエコファーマー制度等を推進し、環境に配慮した農業の振興に努めている。
2.食に対する関心が社会的にも大きな高まりを見せる中、学校給食に対する栄養の教育をどのように取り組もうとしているのか。
県側の答弁
学校給食は市町村教育委員会が実施主体であり、それぞれに栄養士等を配置して、地元の食材を活用したり、行事食や郷土料理を取り入れるなどして、多様な食品の組み合わせによる栄養のバランスのとれた献立を作成し、これをもとに食に関する指導に取り組んでいる。
今後とも、地元の食文化を大切にしながら、食に関する指導の充実を図ってまいりたい。 |
| |
少年犯罪にかかわる事実関係や客観情勢などについて、教育委員会は警察、関係機関と綿密な連携をとり、主体的に情報収集をし、事件の再発防止に取り組まなければならないと考えるがどうか。
県側の答弁
これまで学校は、警察や少年センターなど関係機関との情報交換を定期的に行ってきているが、少年法をはじめ、人権、プライバシーへの配慮等からなかなか主体的に情報収集ができないというのが現状である。
県教育委員会としては、今後、さらに関係機関との信頼関係を密にしながら、許容される範囲において、再発防止の観点から、参考になる情報を一つでも多く得られるように努力をしてまいりたい。 |
| |
医師の確保について、本県離島医師の現状及び医師確保対策について質した。
県側の答弁
離島の医師確保については、離島の全18病院における医療法で定める医師の充足状況は、平成14年度で標準数170人に対し現員数144人で、充足率は85%となっている。
県としては、本年4月、国の補助制度を受け、「長崎県へき地医療支援機構」を設置したが、当該機構は、主に代診医等、短期の医師派遣等に対応することとなっており、常勤医師確保への対応は困難な状況である。
現在、同機構の新たな機能として、平成16年度に常勤医師を離島の市町村立診療所等に派遣する「離島・へき地医療支援センター(仮称)」の設置を県独自の対策として検討している。
設置場所については、従来から救急医療をはじめ、離島医療確保に大きな役割を果たしている国立病院長崎医療センター内に置きたいと考えている。
安定的に医師確保を図るためには、安心できる雇用条件の提示が重要だと考えており、同支援センターの構想として、第一に、身分的には公務員として安定を保証する。第二に、センターに専任医師を配置し、ITを活用し、派遣医師に対する技術支援や相談、助言を行い、また離島に出向いての診療応援等も行うなどの支援体制を確保する。第三に、本人の希望に添った長期の自主研修を保証するといったことを考えている。
今後、なお、同支援センターの設立主体や医師の雇用条件等、調整すべきことも残されているが、早急に対応策を取りまとめてまいりたい。 |
| |
○「防衛庁の省への昇格」に関する請願書
○年金給付額の据え置き等に関する請願書
○「WTO水産物交渉における日本提案実現」を求める意見書採択請願書 |
| |
○警察官の増員に関する意見書
○防衛庁を『省』に昇格することを求める意見書
○義務教育にかかる国庫負担の堅持に関する意見書
○私学助成制度の充実に関する意見書
○年金給付額の据え置き等に関する意見書
○「WTO水産物交渉における日本提案実現」を求める意見書 |
| |
| 【知事提出の議案】 |
| ・予算 |
1件
|
(可決) |
| ・条例 |
7件
|
(可決) |
| ・事件(契約等) |
7件
|
(可決) |
| ・人事 |
1件
|
(同意) |
| ・認定 |
4件 |
(認定3件、継続審査1件) |
|
|
|
| 【議員等提出の議案等】 |
| ・条例 |
1件 |
(可決) |
| ・事件(議員派遣) |
1件
|
(可決) |
| ・意見書 |
6件 |
(可決) |
| ・決議 |
1件 |
(可決) |
|
|
|
| 【請願】 |
3件
|
(採択) |
|
2件 |
(不採択) |
|
|