過去の定例会情報はこちら
主な質問・質疑
●
議案及び採決結果
●
主な質問・質疑
●
会期日程
●
本会議一般質問
● 予算総括質疑
●
意見書・決議
● 議員提案条例
各常任委員会の委員長報告要旨については、こちらをクリックしてください。
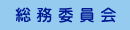
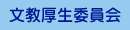
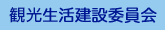
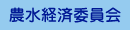
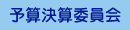
本会議一般質問
| 県北地域の振興対策について |
|
【質問】今後の県北地域の振興対策について、どのような考えのもと、どういった分野に注力していくのか。
【答弁】IR誘致により得られた知見を活かしつつ、IRで目指してきた広域的な周遊観光や多様な雇用の創出等を意識しながら、地域の活性化につなげていく必要がある。地元関係者の皆様や県議会等のご意見を踏まえながら、佐世保市をはじめ、県北地域振興と県全体の発展を目指し、具体的な施策の構築に力を注いでまいりたい。
|
| 知事の様々な疑惑について |
|
【質問】402万円のオートコール、286万円の迂回献金疑惑など様々な政治資金の問題が浮上している件で、県民に不安や疑義を抱かせていることについて、知事は、どのように考えているか
【答弁】県民の皆様へご心配をおかけしていることについて、大変申し訳なく思っている。今後、県民の皆様へ丁寧にご説明したうえでご理解いただくとともに、専門家のご指導もいただきながら、適正の確保に万全を尽くしてまいりたい。
|
| 企業誘致への支援について |
|
【質問】島原市における人口減少に歯止めをかけるためには、企業誘致は重要かつ必要不可欠であり、杉谷地区では新たな工業団地整備に向けた検討が進められているが、島原市への製造業の誘致についての県の取組は。
【答弁】島原市杉谷地区に工業団地が整備された場合、半導体関連や島原半島の豊富な農水産物の活用が期待される食料品製造関連、小型軽量で付加価値の高い医療器具関連などを中心に、積極的な企業誘致を進めてまいりたい。
|
| 小中学校の給食について |
|
【質問】給食によるエネルギーと栄養素の摂取量は、国の基準に対して適正か。また、近年、材料費が高騰しているとは思うが、国の基準と乖離させないことが責務と考える。県の指導はどうか。
【答弁】令和5年度の調査では、摂取量はともに国の基準を下回っていることから、引き続き市町と連携し、栄養管理に関する研修の充実に取り組み、子どもたちの健康保持・増進に努めてまいりたい。また、献立は、保護者等の意見も踏まえて検討されており、必要な栄養素や量についても確認されていると認識している。
|
| 本県における「合計特殊出生率」の実態について |
|
【質問】合計特殊出生率の要素となる各指標の現状や推移、出生率の実態に大きな影響を与える女性の転出超過の状況は。
【答弁】合計特殊出生率の算出に用いられる出生数は、減少傾向が続いており、コロナ禍における出会いの機会の減少等による婚姻数の減少が背景にある。有配偶出生率は、全国と比べると高く、引き続き安心して子育てできる環境づくりとともに結婚支援の充実に努めていく。また、令和5年の外国人を除く女性の転出超過数は3,941人であり、特に20代から30代の女性が2,164人と多く、女性全体の約55%を占めている。
|
| 企業誘致について |
|
【質問】堂崎港埋立地について、南島原市から知事及び議長に対して企業立地に向けた要望がなされており、現在、県と市の間で工業団地として整備するための手続が進められているが、今後どのように企業誘致に取り組んでいくのか。
【答弁】広い面積や熊本県へのアクセスの良さなどの優位性を活かし、食料品製造関連、半導体関連、今後、市場の拡大が見込まれるカーボンニュートラル関連などの企業誘致が考えられる。
|
| 水産業の振興について |
|
【質問】中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)年次会合において、日本の漁獲枠が増枠した場合の国内配分に当たっては、これまでの沿岸漁業者の取組が高く評価され、沿岸漁業者に多く配分されるべきと考えるが、県の認識は。
【答弁】日本の漁獲枠の増枠が実現した場合には、沿岸漁業者のこれまでの努力に対し、次年度以降の配分について配慮されるべきと考えており、様々な機会を捉え、引き続き国に働きかけてまいりたい。
|
| 地裁判決を受けて県はどう対応するのか |
|
【質問】9月9日の地裁判決では、15人の被爆体験者が黒い雨に遭ったと判断され、被爆者として認められた。これを控訴することなく判決を確定してもらいたいが、県の対応は。
【答弁】高齢化が進む被爆体験者の課題解決は、一刻の猶予も許されないとの考えから、9月11日に厚生労働省を訪問し、控訴断念が地元の思いであることを強く伝えた。今後の対応については、国や長崎市と十分に協議を行ったうえで判断していきたい。
|
| 緊急浚渫推進事業の継続の必要性について |
|
【質問】県の管理河川では緊急浚渫推進事業を活用して、堆積土砂の撤去などの対策が行われているが、今後も継続的な浚渫が必要と考える。これまでの事業の実施状況とその効果、今後の取組方針は。
【答弁】令和2年度から令和5年度までの4年間で、事業費は約53億7,000万円、実施箇所数は407か所となっており、治水安全度の確保・向上が図られている。
引き続き、定期的かつ計画的な浚渫を進めてまいりたい。
|
| EBPM(証拠にもとづく政策立案)について |
|
【質問】合理的根拠やエビデンスに基づき政策立案をするEBPMについて、県としてどのように取り組んでいるか。また、具体的な活用事例は。
【答弁】EBPMは、より効果的、効率的な事業を構築していくうえで重要な視点であると認識しており、県総合計画では計画実現に向けた基本姿勢として盛り込むなど、全庁的に推進している。活用事例としては、移動理由アンケート結果を踏まえた移住支援情報の発信、スマート農業技術の導入効果を用いた各地への展開などがある。
|
| パワーハラスメント・カスタマーハラスメント対策 |
|
【質問】働きやすい職場環境にするためにはハラスメントの未然防止が重要であるが、パワーハラスメント及びカスタマーハラスメントの実態は。
【答弁】警察では令和5年中のパワーハラスメントに関する相談は75件、いわゆるカスタマーハラスメントは、昨年の全職員調査で、約41%が著しい暴言等を受けた経験ありと回答があった。知事部局では、全職員を対象とした令和5年度実績調査において、183人からハラスメントがあっていると回答があり、最終的に3件がハラスメントに当たると判断。カスタマーハラスメントは、令和5年度中に65の所属から被害があったとの回答があった。
|
| 魚市場における人材確保対策について |
|
【質問】魚市場では、人材確保がままならず、処理能力が低下している状況にあるが、外国人材の活用を含めた人材不足解消に向けた県の取組は。
【答弁】現在、ミャンマーとベトナムの実習生5名を受け入れているが、法改正によって水産物卸売業では、外国人材を受け入れられなくなることから、各魚市場に水産加工会社との連携などを提案し、検討いただいている。引き続き魚市場の人材不足解消に向けて、国の助言・指導のもと、関係者と連携して取り組んでまいりたい。
|
| |
| 【知事提出の議案】 |
| ・予算 |
1件 |
(可決) |
| ・条例 |
3件 |
(可決) |
| ・事件 |
5件 |
(可決) |
| ・計画 |
1件 |
(可決) |
| ・人事 |
1件 |
(同意) |
| ・認定 |
3件 |
(継続審査) |
| |
| 【議員等提出の案件】 |
| ・議員派遣 |
4件 |
(可決) |
| ・意見書 |
4件 |
(可決) |
| |
| 【請願】 3件(採択2件、不採択1件) |
|